1.明確性要件の判断基準
(判旨抜粋)『特許法36条6項2号は,特許請求の範囲の記載に関し,特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は,仮に,特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には,特許が付与された発明の技術的範囲が不明確となり,第三者の利益が不当に害されることがあり得るので,そのような不都合な結果を防止することにある。そして,特許を受けようとする発明が明確であるか否かは,特許請求の範囲の記載だけではなく,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し,また,当業者の出願当時における技術常識を基礎として,特許請求の範囲の記載が,第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。』
⇒このメルクマールは、明確性要件の判断基準として裁判例上確立している。
2.明細書の記載に基づく、明確性要件適合性の判断(結論は明確性要件×)
(判旨抜粋)『…請求項1の記載からは,粉砕工具の「工具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン粒径の意義が明らかであるとはいえない。また,本件特許の出願当時において,炭化タングステンを含んでなる表面を有する粉砕工具の工具表面に含有される炭化タングステン粒子につき,質量により秤量したメジアン粒径を得ることができたとする当業者の技術常識を認めるに足りる証拠はない。…
本件明細書には,「炭化タングステンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の「工具表面」のタングステン含有量が95%以下であり,工具表面の材料における100%に対する残りは,好ましくはコバルト結合剤であり,好ましくは1%未満の程度に追加の炭化物が存在する(…),焼結の結果は,炭素の添加によっても影響を受ける(…)との記載があり,「炭化タングステンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の「工具表面」の炭化タングステン粒子が,コバルトである結合剤と焼結により一体化していることが開示されている。そして,本件明細書には,コバルト結合剤と焼結により一体化した「粉砕工具」の「工具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン粒径について,定義や測定方法の記載はない。…
以上によれば,本件明細書の記載を考慮し,出願当時の技術常識を基礎としても,本件発明の「炭化タングステンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の「工具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン粒径の意義を理解することはできず,本件発明の技術的範囲は不明確といわざるを得ない…。』
⇒特許明細書中の発明の詳細な説明に、“パラメータ”・“数値”の測定方法を必ず記載すべきである。明確性要件違反の問題に加えて、特許侵害訴訟における充足論において、全ての合理的な測定方法で充足しなければならないとされる裁判例が多数あり(後掲)、この枠組みで充足性が判断された事案では、特許権者が全敗である。何れにしても、数値の測定方法を記載するデメリットは少ない。
3.明細書以外の外部証拠に基づく「測定方法」の特定(結論は「特定できず」)
(判旨抜粋)『粒子の大きさを測定する方法としてストークス径を得る沈降法があることが周知であり,沈降法により重量(質量)基準に基づく粒度分布が得られるとしても,「粉砕工具」の「工具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子が,コバルトである結合剤と焼結により一体化している以上,沈降法により炭化タングステン粒子のストークス径を測定することは不可能であるから,本件発明の「炭化タングステン粒子の質量により秤量されたメジアン粒径」が,沈降法に基づいて得られるストークス径のメジアン粒径であると解することはできない。』
⇒被告製品においてクレームアップされたパラメータ・数値を測定すること自体ができず、充足性を立証できなかった事案もあるから(後掲)、現実に測定が困難な“パラメータ”・“数値”をクレームアップすることは避けるべきである。
★数値(パラメータ)が多義的な場合の、明確性要件、充足性について(筆者がパテント誌Vol.71, No.6, p21-32「数値限定発明の充足論、明確性要件」において述べた内容を敷衍する。)
1.①数値(パラメータ)の測定条件により測定結果が異なる場合
(1)この場合、測定条件が明細書の記載又は出願当時の技術常識から導かれるのであれば、当該測定条件による測定結果に基づいて属否が決まる。
この点が争われ、特許権者が勝訴した裁判例は2件ある。知財高判平成17年(行ケ)第10661号(「オレフィン共重合体の製造方法」事件)は、出願当時の技術常識からユニポール法の測定条件は「ふるい分け法」によることを理解できるとした。東京地判平成19年(ワ)第3493号(「経口投与用吸着剤」事件)は、回折強度の測定条件はJIS、日本薬局方、日本学術振興会の定めた測定法が共通していたため、理解できるとした。
(2)この場合、測定条件が明細書の記載又は出願当時の技術常識から導かれるのであれば、他方、この点が争われ、特許権者が敗訴した裁判例として、明確性要件違反と判断された裁判例は3件ある。知財高判平成25年(行ケ)第10172号(「渋味のマスキング方法」事件)は、スクラロース量の数値範囲との関係で「甘味を呈さない量」がどの範囲の量を意味するかが不明確であるとした。知財高判平成23年(行ケ)第10418号(「防眩フィルム」事件)及び、知財高判平成28年(行ケ)第10187号(「水性インキ組成物」事件)は、測定条件が明細書の記載又は出願当時の技術常識から導かれないとした。
(3)また、「従来より知られたいずれの方法によって測定しても,特許請求の範囲の記載の数値を充足する場合でない限り,特許権侵害にはならない」として、被疑侵害者側の測定結果に基づいて非充足とされた裁判例は4件あり、東京地判平成11年(ワ)第17601号(「感熱転写シート」事件)、東京地判平成14年(ワ)第4251号、東京高判平成15年(ネ)3746号「マルチトール含蜜結晶」事件)、東京地判平成23年(ワ)第6868号(「シリカ質フィラー」事件)、東京地判平成24年(ワ)第6547号、知財高判平成27年(ネ)第10016号(「ティシュペーパー」事件)である。
特に、「ティシュペーパー」事件は、明細書中にJIS規格が明示されていたにもかかわらず、JIS規格に規定がない7個の測定条件について、従来より知られたいずれの方法によって測定しても充足する必要があるとして非充足とされており、厳しい判決であるという評釈がある。他方、公知公用の無効理由を立証し難いパラメータ特許発明であり、パラメータも出願当時の規格を微修正したものに過ぎなかったことから、侵害訴訟において特許権者勝訴と判決することは躊躇される事案であったかもしれない。
この類型では、「従来より知られたいずれの方法によって測定しても,特許請求の範囲の記載の数値を充足する」か否かの審理に入ると全てのケースで特許権者が敗訴しているため、特許権者としては、明細書等又は技術常識から特許権者の測定条件が一義的に導かれると主張するべきである。「従来より知られたいずれの方法によって測定しても,特許請求の範囲の記載の数値を充足する」か否かという土俵に乗った上で、被告の測定結果の“信憑性”を争う議論に拘泥してしまうと、過去のケースでは特許権者が全敗なのである。したがって、特許権者としては明細書中に測定条件を明記すべきであり、これを明記しないメリットは無く、デメリットは計り知れない。
なお、「感熱転写シート」事件判決は、原告先願の明細書に記載されていた測定条件に基づくことができない理由として、先願明細書が本件明細書に引用されていなかったことを指摘した。先願明細書が明細書中に引用されている場合は、その記載を主張する余地もある。
この類型に関わる留意点として、従来より知られた測定条件が複数あり、明細書において測定条件が一義的に特定されていない場合、具体的な測定条件をクレームアップした方が発明の技術的範囲が広くなる(通常の感覚とは逆である)という点がある。何故なら、具体的な測定条件がクレームアップされていないと、「従来より知られた測定条件」の何れでも充足しなければならないからである。したがって、具体的な測定条件を訂正で追記することは、(特許庁は許すかもしれないが、)発明の実質的拡張(特許法126条6項)に該当し、回復不可能な無効理由(特許法123条1項8号)となる懸念があるため、クレームアップすることは避け、明細書等又は技術常識から測定条件を理解できると主張するに留めることが望ましい。
なお、「前記屈折率の値は、JIS K 7142に従って測定される測定値であり、…」という測定条件を追記する訂正が新規事項追加であるとして認められなかった裁判例として、知財高判平成27年(行ケ)第10234号(「透明不燃性シート」事件)がある。
2.②パラメータ自体の技術的意義が多義的である場合
この場合は、明確性要件(特許法36条6項2号)違反とされる。
例えば、知財高判平成28年(行ケ)第10005号(「眼科用清涼組成物」事件<一次判決>)は,「平均分子量」が、「重量平均分子量」であるか「粘度平均分子量」であるかにつき、明細書中に前者を意味すると理解できる記述と、後者を意味すると理解できる記述とが混在していたため、何れを意味するか不明であるとして、明確性要件違反と判断した。
また、知財高判平成20年(ネ)第10013号(「遠赤外線放射体」事件)は,「平均粒子径」が、「体積相当径」であるか「二次元的に定義される径」であるか、その定義(算出方法)が明細書に記載されていないことを理由に,明確性要件違反と判断した。
一般論としては、上記類型①において測定条件を明細書中に明記すべきであったと同様に、パラメータを一義的に理解できるように具体的に明記すべきである。もちろん、発明者は一義的に特定したという認識であろうから、知的財産部ないし外部特許事務所の弁理士が注意喚起をすることが望ましい。なお、上掲した「眼科用清涼組成物」事件<一次判決>においては、実施例の記載では「重量平均分子量」を意味すると理解できたものの、出願当時の他社製品の「平均分子量」を他社公表に係る数値をそのまま記載してしまったところ、当該数値は「粘度平均分子量」であったという事案である。この事例から、実施例等においてパラメータが一義的であるように具体的に明記した上で、余計な情報を記載しないという方針が望ましいといえる。明細書中の実施例・比較例同士の不整合を理由に、明確性要件違反のみならず、サポート要件違反と判断された事案もあるため、要注意である。
3.小括
以上のとおり、パラメータの多義性については、①測定条件により測定結果が異なる類型と、②パラメータの技術的意義が多義的である類型がある。類型①は、従来より知られた方法が複数存在したか否かが主戦場であり、被疑侵害者としては、これが複数存在したという土俵に乗れば、過去の裁判例は何れも請求棄却となっている。類型②は、パラメータというクレーム文言解釈の問題であるから、特許法70条1項・2項に従った通常の議論である。この意味で、両類型は主張・立証対象が異なるため、混同せずに対応することが肝要である。
本判決(令和元年(行ケ)第10095号)で問題となった発明は、「①測定条件により測定結果が異なる類型」の一つであり、従来の裁判例と整合するものである。
4.更なる考察(被告製品に適用困難な測定方法)
本判決の事案において、仮に発明の詳細な説明において「ストークス径を得る沈降法」により測定すると記載されていたとすれば、明確性要件は適合したかもしれない。
しかしながら、当該特許権を行使する際には、もう一段階の論点がある。すなわち、明細書中の発明の詳細な説明に記載された測定方法が被告製品に適用困難であり、現実に測定できない場合は、充足論につき立証不十分であるとして特許権者敗訴となる。
例えば、知財高判平成20年(ネ)第10073号「ソーワイヤ用ワイヤ事件」は、「本件発明の構成要件Cにいう『ワイヤ表面から15μmの深さまでの層除去』というのは,ワイヤ表面から15μm層除去したことを意味するというべきであるから,エッチング深さは本来15μmでなければならないというべきであり,それが困難であるとしても,少なくとも『ワイヤ表面から15μmの層除去した数値』を的確に推認することができる立証がなされなければならないのであって,エッチング深さが『13~17μm』のものを選別して,それを平均するだけでは足らないというべきである。…原告は,甲33(…)によって,同一のワイヤについて,エッチング深さが15μmである場合と16μmである場合とで内部応力値の相違は0.11kg/mm にすぎないと主張する。しかし,…甲33には,次の2点において問題があり,この点に補正を加える必要がある。」と判示して、特許権者敗訴とした。
また、大阪地判平成16年(ワ)第7239号「タッチスイッチ事件」は、「本件考案については…『基板の凹凸の平均粗さ(Rz)が0.5~50μmとされている微細な凹凸を形成してなる』ものと規定しているところ、これについて、本件明細書には、『JIS B 0601に基づく凹凸の平均粗さ(Rz)を、0.5~50μmとする。』との記載しか存在せず、本件実用新案登録出願当時の1982年JIS規格によれば、この意味は、基板の凹凸について、基準長さ0.25mmで測定した十点平均粗さが0.5μm以上であり、基準長さ8mmで測定した十点平均粗さが50μm以下であることを意味するものであると解されるものの、上記基準長さにより十点平均粗さの測定を試みた際に基板の断面曲線に山頂と谷底がそれぞれ5個以上存在しないときの測定方法については、本件明細書や、1982年JIS規格とその解説のいずれにも記載がなく、当業者の技術常識としても存在しなかったと認められるところである。
したがって、本件明細書に接した当業者において本件考案を実施することができるというためには、上記基準長さを用いて基板の凹凸の十点平均粗さの測定を試みた際に、その断面曲線に山頂と谷底がそれぞれ5個以上存在しない測定点は、これを考慮せず、もし、基板上に、断面曲線に山頂と谷底がそれぞれ5個以上存在する測定点が存在しない場合は、そのような基板を用いた対象物件は本件考案の構成要件C②を充足しないものと解するべきである。
なぜならば、このように解さなければ、断面曲線に山頂と谷底がそれぞれ5個以上存在する測定点が存在しないような基板を用いた対象物が本件考案の技術的範囲に属するか否かについて、当業者においては、本件明細書の記載と技術常識から明確な判断をすることができず、…当業者において、本件明細書の記載と技術常識に基づいて、本件実用新案権を侵害することを回避することすらできなくなるからである。」と判示して、特許権者敗訴とした。
(1) 明確性要件の判断基準
特許法36条6項2号は,特許請求の範囲の記載に関し,特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は,仮に,特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には,特許が付与された発明の技術的範囲が不明確となり,第三者の利益が不当に害されることがあり得るので,そのような不都合な結果を防止することにある。そして,特許を受けようとする発明が明確であるか否かは,特許請求の範囲の記載だけではなく,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し,また,当業者の出願当時における技術常識を基礎として,特許請求の範囲の記載が,第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。
(2) 本件発明の明確性について
ア
イ
ウ
(3)原告の主張について
ア
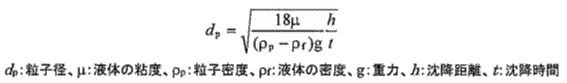
とのストークスの式が記載されている。これらによれば,沈降法は,重量(質量)基準に基づく粒度分布が得られるものであること,液相中の粒子の沈降速度から粒径を求めるものであり,分離して沈降可能な粒子を測定対象としていることが認められる。
イ
ウ
エ
(4)小括
よって,本件発明の「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」の意味するところは明確とはいえず,請求項1の記載は,第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるというべきであり,これを引用する請求項2~4,8,11も,いずれも,不明確であるというべきである。したがって,取消事由1は理由がない。
原告(特許出願人):ワッカー ケミー アクチエンゲゼルシャフト
被告:特許庁長官
執筆:高石秀樹(弁護士・弁理士)(特許ニュース令和2年6月1日の原稿を追記・修正したものです。)
監修:吉田和彦(弁護士・弁理士)
本件に関するお問い合わせ先: h_takaishi@nakapat.gr.jp
〒100-8355 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル6階
中村合同特許法律事務所